【日本ラクロスの四半世紀・第14回】 特集・開拓者からのメッセージ(1) 「世界への挑戦」
2012/05/16
1986年~1997年の12年間で、日本のラクロスは北海道から九州にまで広がり、また世界大会を国内で開催するまでに育ちました。
日本ラクロスの土台が形成されたこの時期に携わった選手・審判員・スタッフたちは、参考とする事例もない中で、ラクロスをもっと楽しみ、もっと発展させるために、自ら壁にぶつかっていき、その経験を元に、今の日本ラクロスの土台を一つ一つ築き上げていったのです。
そして、この「自分達の環境は常に自分達で整える」という意志は、四半世紀を過ぎた今日においても、日本ラクロスの文化として、ラクロスに関わる人たちの中に息づいています。
この25周年企画では、特集として、当時の協会機関誌『RELAX2』に掲載された、この時期にラクロスに関わった人たちが自分たちの想いを書き綴ったエッセイを再掲していきます。
第一弾となる今回は、1996年・1997年の時、世界に挑戦した選手・審判員たち3名のエッセイです。
もっとラクロスで強くなるために、もっとラクロスを楽しむために、もっとラクロスにのめり込み、自分の手でもっと素晴らしいラクロスの環境を手に入れる。言葉の端々に、そんな日本ラクロスへの熱い思いが込められている彼ら・彼女らのメッセージを、ぜひご覧ください。


皆さん、こんにちは。私はバックネル大学(アメリカ・ペンシルバニア州)でラクロスをしている吉留太郎といいます。今年の1月でアメリカでの生活も1年が過ぎました。まず、アメリカに渡った経緯を話しますと、私が法政で2年生の夏にアメリカのラトガースキャンプに参加し、そこでバックネルのヘッドコーチであるシド・ジェーミソンに出会いました。そこで彼はゲームの審判をしていて、ゲーム終了後に僕に近付いて来て「君の専攻は何だい?私の大学でラクロスをやらないか?」と聞いてきたのです。当時の私にとって、アメリカで勉強をしながらラクロスをするなんてことは夢以上のもので、これっぽっちも考えた事がなかったので、その時はその場で断りました。しかし、偶然に1年後の6月にバックネルが日本に国際親善試合でやってきたのです。この時も彼は私を再びバックネルに誘ってくれたのです。
そして7月、イギリスで行われたワールドカップが私の心を変えました。日本がいかに世界のラクロスシーンにおいて若い国なのかということ、そして、いくら選手にスピードや個人能力があっても、それを生かす組織的な戦術や練習法を知らなければ世界では勝てないことをワールドカップは教えてくれました。言い換えれば、戦術さえ知っていれば勝てるという手応えがあったのです。だから、元来負けず嫌いの私はどうしても「世界の舞台で1勝する」という夢を諦めることが出来なかったのです。そして、昨年の1月、私はその1勝を目指し、バックネルのラクロス部の門をたたきました。
昨年のバックネルの成績は12勝0敗。ディビジョン1で唯一の無敗チームでした。そしてナショナルランキング9位でありながら、NCAAトーナメント(全米一を決める決勝トーナメント)に出場できる12校の中に選ばれなかったのです。アメリカというと自由の国というイメージがありますが、やはりスポーツの世界でも様々な偏見や政治的なコネなどの腐食した一面もあるのです。そのため、今年は全米中がバックネルの行く末に注目しています。今後、バックネルがNCAAトーナメントに出場するためには、今年はとても大切なシーズンなのです。
そんなこともあって、私達は本当に死んでしまうのではと思うくらい練習してきました。月から土曜日まで2時間の練習に合計3キロのダッシュ、そして2時間の筋トレを毎日続けています。しかし、今年はスターティングメンバーの半分以上が2年生という若いチームであることも重なって、現在は1勝3敗と負け越しています。日本の皆さんも経験していると思いますが、チームというのは負け続けると本当に勝つことが難しくなってきます。コーチは毎日のように怒鳴りたてるし、ラクロスをすることさえ苦痛になってきます。しかし、私はこのように中々勝てない状況の中で経験することが、将来世界の舞台で勝つために必要な経験になるように思います。そして、バックネルラクロスも今、体験していることを乗り越えれば、きっとNCAAトーナメントに出場できると信じています。とにかく私は頑張ります。まだまだギブアップなんか言えません。
(『RELAX2・第1号;1997年5月』より)
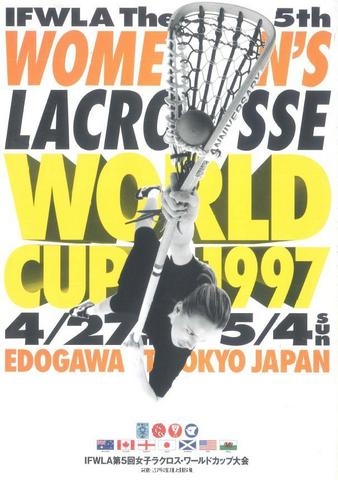

-ラクロスよ、文化たれ-。このフレーズを知っている人も、もう少なくなってきただろう。これは91年の国際親善試合ポスターに書かれていた言葉である。この国際親善試合は、私が日本代表になりたいと思ったきっかけの大会でもあった。97年、私は日本代表選手としてワールドカップに出場した。そして、そこで文化を実感した。
同じラクロスとはいえ、オーストラリアのパワーラクロス、イングランドのパスワーク、アメリカの底力など、それぞれにその国の文化を垣間見ることができた。しかし、私が最も違いを感じたのは、諸外国ではなく、関西と関東といった日本国内での文化の違いだった。
以前、私は「大阪学」という本を読んだ。それは大阪の文化について触れているのだが、分かりやすいように関西と関東の文化を比べ、その違いが記されていた。そもそもこれらの地域の文化の違いは、歴史が大きくかかわっている。江戸時代には東京(江戸)は武士の街であり、大阪は商業の町であった。
武士の社会は封建社会であり、その秩序を保つことにより存立し、建前が何よりも大事であった。人に弱みを見せることを恐れ、自分の格を上げ、箔をつけることが美徳とされた。それに比べ、商人は政治という秩序に頼らず、自分の才覚で道を切り開く、競争社会であった。関西の人は本音でものを言う。建前で格好良くしようという気持ちがない。時にはこれが相手には、ずばり心に踏み込まれる思いをさせる。だからよく、関西の人は図々しくて、恐いイメージが先行する。
そう言えば思い当るふしがある。関西と関東の強化選手団が集まった時、一人の関西の選手が「関東の人って、脱いでも脱いでもJAPANですね」ともらした。確かにそうだった。キャップからスウェット、Tシャツ、ウインドブレーカーまで、どこを見てもJAPANの文字でうめられていた。周りの人も、あの人はJAPANだから偉い。JAPANだからあの人の言うことは正しい。と、思っているみたいだった。
こんなことを言っていると、関西と関東の選手達は一緒にプレーできないじゃないかと思われるかもしれないが、それは絶対に違う。例えば日本代表なら、チームの選考段階から、チームの方針をしっかり立て、それに見合った選手を選び、練習すれば、日本中どこに住んでいようが、息のあったチームプレーができるはずだ。ただ、残念ながら、今回のワールドカップではそれができなかったように思う。
私の家の近所には、吉本興業の”なんば花月”がある。そこでは毎日、芸人がデブ、チビ、ハゲなど、自分の欠点をさらけ出し、それをネタに笑いをとっている。私は関西で生まれ、関西人に囲まれて生きてきた。そして、大学でラクロスと出会い、夢にまで見た日本代表になった。今回、日本代表として1年以上の活動の中で、文化の違う選手達と共に行動し、改めて思った。私は千日前の陶器屋の娘なんだ、と。
(『RELAX2・第3号;1997年9月』より)
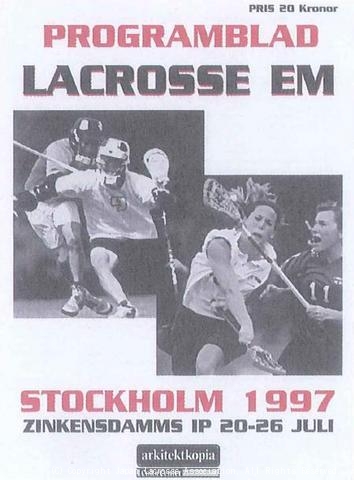

~ラクロスの仲間って、どこへ行っても同じよね~
アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本と世界各国から縦縞シャツに黒のスカート姿の女性が集まった場所は、スウェーデン、ストックホルム。7月20日から26日まで、ラクロスヨーロッパ選手権が開催された。参加国はスウェーデン、イングランド、ウェールズ、スコットランド、ドイツ、チェコの6チーム。そして、各国の審判員の中に、私もいた。
経験豊かな国際審判員、1級レベルの審判員に囲まれて、2級の私はめったにないチャンスと期待もあったが、まずは緊張と不安で一杯だった。いくら緊張していても、2級でも、ヨーロッパ選手権の一審判員として派遣されていることには変わりなく、他の審判員もそのように扱うし、ハーフタイムには、各国のコーチや選手が真剣にジャッジやルールに関して説明を求めてくる。一日一回は笛を吹く試合があり、様々な場面を経験することによって、審判員としての自覚も徐々に高まっていった。最終日には、自分なりにうまい審判ができたとか、楽しんでできたとまでは言えないが、威厳と自覚を持って精一杯試合に臨むことができた。日本に帰っても、この緊張感を忘れずにどんな試合にも臨んでいかなければ、そして、もっと勉強しなければと、新たな刺激も生まれ、本当にいい経験になった。日本からは私の他にも女子の審判員が2名、男子の審判員が2名、そして事務局長と、来年のワールドカップに向けてのスカウティングで男子のコーチがきていた。また、ドイツから観戦に駆け付けた女子ラクロッサーもいた。遠いヨーロッパの大会なのに、これだけ多くの日本人が集まって頑張っていることも誇りに思えた。
ストックホルムでは、こんなこともあった。女子の審判員みんなで夕食を食べにいく機会があった。最初のうちは、どんなメニューにするとか、お買い物の話とか、近所のおばさんの井戸端会議かのような様子を見せていたのだが、しばらくすると、話題はラクロスへと移行し、その話で盛り上がっている。「待て・・・、この気分は日本でも味わったことがあるぞ・・・」と、同じようなシーンが思い浮かんだ。それはチーム(私は名古屋ラクロスクラブというクラブチームに所属している)でご飯を食べにいくと、男の子の話やら会社の話をしていたかと思ったら、最後には熱くラクロスの話で盛り上がっている・・・。ラクロスの仲間って、どこへ行っても同じよねと実感。ラクロスっていう共通点だけで、国を越えて、ここまで盛り上がれる集まりが楽しく、心地よかった。
今回のストックホルムで再認識したことが二つ。審判って難しいってことと、私ってやっぱりラクロスが好きなんだ!ってこと。さて、いよいよ秋のリーグ。新鮮な気持ちで、審判にプレーにおもいっきり楽しもう。
(『RELAX2・第4号;1997年11月』より)
■ 『第15回 1998年・全国のチームに全日本選手権の道を』 へ続く
■ 『Japan Lacrosse History ~日本ラクロスの四半世紀~』 記事一覧に戻る


日本ラクロスの土台が形成されたこの時期に携わった選手・審判員・スタッフたちは、参考とする事例もない中で、ラクロスをもっと楽しみ、もっと発展させるために、自ら壁にぶつかっていき、その経験を元に、今の日本ラクロスの土台を一つ一つ築き上げていったのです。
そして、この「自分達の環境は常に自分達で整える」という意志は、四半世紀を過ぎた今日においても、日本ラクロスの文化として、ラクロスに関わる人たちの中に息づいています。
この25周年企画では、特集として、当時の協会機関誌『RELAX2』に掲載された、この時期にラクロスに関わった人たちが自分たちの想いを書き綴ったエッセイを再掲していきます。
第一弾となる今回は、1996年・1997年の時、世界に挑戦した選手・審判員たち3名のエッセイです。
もっとラクロスで強くなるために、もっとラクロスを楽しむために、もっとラクロスにのめり込み、自分の手でもっと素晴らしいラクロスの環境を手に入れる。言葉の端々に、そんな日本ラクロスへの熱い思いが込められている彼ら・彼女らのメッセージを、ぜひご覧ください。
|
吉留 太郎 「アメリカで見る夢」 |
日本人初のNCAAプレイヤー(1996年~ディビジョン1・バックネル大学に所属) 1998年にはディヴィジョン1・オールパトリオットリーグのファーストチームに選出。 |
|
加藤 祐子 「文化の壁」 |
1997年女子日本代表 国内で初開催となった女子世界大会で、チーム最多得点をあげる活躍。 |
|
熊澤 一美 「やっぱりラクロスが好き!」 |
日本ラクロス協会公認審判員 1997年ラクロスヨーロッパ選手権(ストックホルム)に参加するなど、国内外で活動。 |
| アメリカで見る夢 (吉留 太郎) |


皆さん、こんにちは。私はバックネル大学(アメリカ・ペンシルバニア州)でラクロスをしている吉留太郎といいます。今年の1月でアメリカでの生活も1年が過ぎました。まず、アメリカに渡った経緯を話しますと、私が法政で2年生の夏にアメリカのラトガースキャンプに参加し、そこでバックネルのヘッドコーチであるシド・ジェーミソンに出会いました。そこで彼はゲームの審判をしていて、ゲーム終了後に僕に近付いて来て「君の専攻は何だい?私の大学でラクロスをやらないか?」と聞いてきたのです。当時の私にとって、アメリカで勉強をしながらラクロスをするなんてことは夢以上のもので、これっぽっちも考えた事がなかったので、その時はその場で断りました。しかし、偶然に1年後の6月にバックネルが日本に国際親善試合でやってきたのです。この時も彼は私を再びバックネルに誘ってくれたのです。
そして7月、イギリスで行われたワールドカップが私の心を変えました。日本がいかに世界のラクロスシーンにおいて若い国なのかということ、そして、いくら選手にスピードや個人能力があっても、それを生かす組織的な戦術や練習法を知らなければ世界では勝てないことをワールドカップは教えてくれました。言い換えれば、戦術さえ知っていれば勝てるという手応えがあったのです。だから、元来負けず嫌いの私はどうしても「世界の舞台で1勝する」という夢を諦めることが出来なかったのです。そして、昨年の1月、私はその1勝を目指し、バックネルのラクロス部の門をたたきました。
昨年のバックネルの成績は12勝0敗。ディビジョン1で唯一の無敗チームでした。そしてナショナルランキング9位でありながら、NCAAトーナメント(全米一を決める決勝トーナメント)に出場できる12校の中に選ばれなかったのです。アメリカというと自由の国というイメージがありますが、やはりスポーツの世界でも様々な偏見や政治的なコネなどの腐食した一面もあるのです。そのため、今年は全米中がバックネルの行く末に注目しています。今後、バックネルがNCAAトーナメントに出場するためには、今年はとても大切なシーズンなのです。
そんなこともあって、私達は本当に死んでしまうのではと思うくらい練習してきました。月から土曜日まで2時間の練習に合計3キロのダッシュ、そして2時間の筋トレを毎日続けています。しかし、今年はスターティングメンバーの半分以上が2年生という若いチームであることも重なって、現在は1勝3敗と負け越しています。日本の皆さんも経験していると思いますが、チームというのは負け続けると本当に勝つことが難しくなってきます。コーチは毎日のように怒鳴りたてるし、ラクロスをすることさえ苦痛になってきます。しかし、私はこのように中々勝てない状況の中で経験することが、将来世界の舞台で勝つために必要な経験になるように思います。そして、バックネルラクロスも今、体験していることを乗り越えれば、きっとNCAAトーナメントに出場できると信じています。とにかく私は頑張ります。まだまだギブアップなんか言えません。
(『RELAX2・第1号;1997年5月』より)
| 文化の壁 (加藤 祐子) |
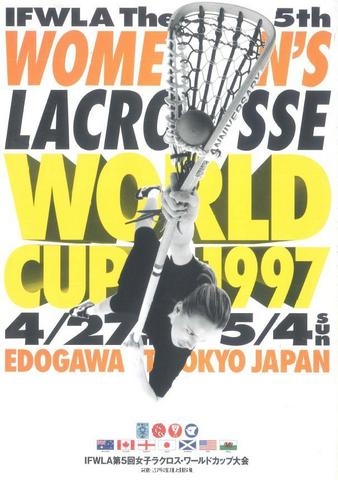

-ラクロスよ、文化たれ-。このフレーズを知っている人も、もう少なくなってきただろう。これは91年の国際親善試合ポスターに書かれていた言葉である。この国際親善試合は、私が日本代表になりたいと思ったきっかけの大会でもあった。97年、私は日本代表選手としてワールドカップに出場した。そして、そこで文化を実感した。
同じラクロスとはいえ、オーストラリアのパワーラクロス、イングランドのパスワーク、アメリカの底力など、それぞれにその国の文化を垣間見ることができた。しかし、私が最も違いを感じたのは、諸外国ではなく、関西と関東といった日本国内での文化の違いだった。
以前、私は「大阪学」という本を読んだ。それは大阪の文化について触れているのだが、分かりやすいように関西と関東の文化を比べ、その違いが記されていた。そもそもこれらの地域の文化の違いは、歴史が大きくかかわっている。江戸時代には東京(江戸)は武士の街であり、大阪は商業の町であった。
武士の社会は封建社会であり、その秩序を保つことにより存立し、建前が何よりも大事であった。人に弱みを見せることを恐れ、自分の格を上げ、箔をつけることが美徳とされた。それに比べ、商人は政治という秩序に頼らず、自分の才覚で道を切り開く、競争社会であった。関西の人は本音でものを言う。建前で格好良くしようという気持ちがない。時にはこれが相手には、ずばり心に踏み込まれる思いをさせる。だからよく、関西の人は図々しくて、恐いイメージが先行する。
そう言えば思い当るふしがある。関西と関東の強化選手団が集まった時、一人の関西の選手が「関東の人って、脱いでも脱いでもJAPANですね」ともらした。確かにそうだった。キャップからスウェット、Tシャツ、ウインドブレーカーまで、どこを見てもJAPANの文字でうめられていた。周りの人も、あの人はJAPANだから偉い。JAPANだからあの人の言うことは正しい。と、思っているみたいだった。
こんなことを言っていると、関西と関東の選手達は一緒にプレーできないじゃないかと思われるかもしれないが、それは絶対に違う。例えば日本代表なら、チームの選考段階から、チームの方針をしっかり立て、それに見合った選手を選び、練習すれば、日本中どこに住んでいようが、息のあったチームプレーができるはずだ。ただ、残念ながら、今回のワールドカップではそれができなかったように思う。
私の家の近所には、吉本興業の”なんば花月”がある。そこでは毎日、芸人がデブ、チビ、ハゲなど、自分の欠点をさらけ出し、それをネタに笑いをとっている。私は関西で生まれ、関西人に囲まれて生きてきた。そして、大学でラクロスと出会い、夢にまで見た日本代表になった。今回、日本代表として1年以上の活動の中で、文化の違う選手達と共に行動し、改めて思った。私は千日前の陶器屋の娘なんだ、と。
(『RELAX2・第3号;1997年9月』より)
 |
プロフィール |
神戸ラクロスクラブ所属(当時)。 女子日本代表のアタッカーとして、第5回IFWLA女子ワールドカップに出場。 ウェールズ戦(1得点)、スコットランド戦(2得点)、カナダ戦(2得点)と、チーム最多の5得点をあげる活躍を見せた。 |
| やっぱりラクロスが好き! (熊澤 一美) |
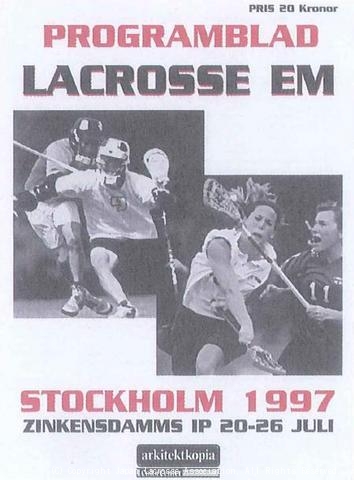

~ラクロスの仲間って、どこへ行っても同じよね~
アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本と世界各国から縦縞シャツに黒のスカート姿の女性が集まった場所は、スウェーデン、ストックホルム。7月20日から26日まで、ラクロスヨーロッパ選手権が開催された。参加国はスウェーデン、イングランド、ウェールズ、スコットランド、ドイツ、チェコの6チーム。そして、各国の審判員の中に、私もいた。
経験豊かな国際審判員、1級レベルの審判員に囲まれて、2級の私はめったにないチャンスと期待もあったが、まずは緊張と不安で一杯だった。いくら緊張していても、2級でも、ヨーロッパ選手権の一審判員として派遣されていることには変わりなく、他の審判員もそのように扱うし、ハーフタイムには、各国のコーチや選手が真剣にジャッジやルールに関して説明を求めてくる。一日一回は笛を吹く試合があり、様々な場面を経験することによって、審判員としての自覚も徐々に高まっていった。最終日には、自分なりにうまい審判ができたとか、楽しんでできたとまでは言えないが、威厳と自覚を持って精一杯試合に臨むことができた。日本に帰っても、この緊張感を忘れずにどんな試合にも臨んでいかなければ、そして、もっと勉強しなければと、新たな刺激も生まれ、本当にいい経験になった。日本からは私の他にも女子の審判員が2名、男子の審判員が2名、そして事務局長と、来年のワールドカップに向けてのスカウティングで男子のコーチがきていた。また、ドイツから観戦に駆け付けた女子ラクロッサーもいた。遠いヨーロッパの大会なのに、これだけ多くの日本人が集まって頑張っていることも誇りに思えた。
ストックホルムでは、こんなこともあった。女子の審判員みんなで夕食を食べにいく機会があった。最初のうちは、どんなメニューにするとか、お買い物の話とか、近所のおばさんの井戸端会議かのような様子を見せていたのだが、しばらくすると、話題はラクロスへと移行し、その話で盛り上がっている。「待て・・・、この気分は日本でも味わったことがあるぞ・・・」と、同じようなシーンが思い浮かんだ。それはチーム(私は名古屋ラクロスクラブというクラブチームに所属している)でご飯を食べにいくと、男の子の話やら会社の話をしていたかと思ったら、最後には熱くラクロスの話で盛り上がっている・・・。ラクロスの仲間って、どこへ行っても同じよねと実感。ラクロスっていう共通点だけで、国を越えて、ここまで盛り上がれる集まりが楽しく、心地よかった。
今回のストックホルムで再認識したことが二つ。審判って難しいってことと、私ってやっぱりラクロスが好きなんだ!ってこと。さて、いよいよ秋のリーグ。新鮮な気持ちで、審判にプレーにおもいっきり楽しもう。
(『RELAX2・第4号;1997年11月』より)
■ 『第15回 1998年・全国のチームに全日本選手権の道を』 へ続く
■ 『Japan Lacrosse History ~日本ラクロスの四半世紀~』 記事一覧に戻る


« 【日本ラクロスの四半世紀・第13回】 1997年・女子世界大会開催と新たな取り組み | 【日本ラクロスの四半世紀・第15回】 1998年・全国のチームに全日本選手権への道を »
記事一覧
- 【日本ラクロスの四半世紀】 パイオニアからのメッセージ集 [2012/12/31]
- 【日本ラクロスの四半世紀・第33回】 特集・開拓者からのメッセージ(5) 「全国各地区より」 [2012/12/31]
- 【日本ラクロスの四半世紀・第32回】 2012年・全日本選手権5連覇と大学チーム優勝 [2012/12/30]
- 【日本ラクロスの四半世紀・第31回】 特集・開拓者からのメッセージ(4) 「海外留学」 [2012/12/23]
- 【日本ラクロスの四半世紀・第30回】 2011年・全国各地のチーム・審判・スタッフの活躍 [2012/12/15]
 一般社団法人日本ラクロス協会 アーカイブサイト「.Relax」
一般社団法人日本ラクロス協会 アーカイブサイト「.Relax」
